日経NEEDSモデル ( MACROQ60 ) の問題点
乗数効果が小さすぎることの原因と思われること
乗数効果は、家計消費を主要内容とする民間最終消費が、自生的最終需要支出が増やされたことによってどのように増加することになるかということによって、決まってくる。この「日経モデル」では、民間最終消費を決定する因果連鎖は、およそ下記に図示したループ型の連鎖とされている。丸括弧内の数字は方程式番号である。
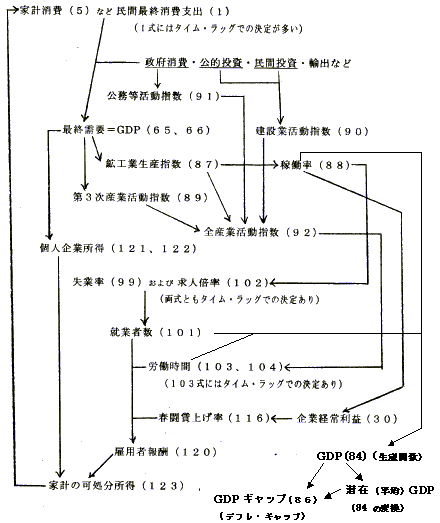
この図の最上部に示された民間最終消費支出関数(第1式)は、多元回帰推定によるstochasticな関数であるが、変化率関数ではないうえに、タイム・ラッグが多用されており、被説明変数(すなわち民間最終消費支出)それ自体の「1期前の値」を主要な説明変数として用いているほか、当該期から3期前までの家計可処分所得をも説明変数としているために、この関数は、本質的に、当該期に発生したなんらかの衝撃から生じるような波動的な動きをフォローしうるような特性には乏しく、主として過去の期間の値からの惰性で被説明変数の値が決まるという傾向を強く持っている。すなわち、この関数は、当該期において自生的に発生した外生的な変化への感応性が弱い鈍感な関数であると、見なければならない。このような波動をフォローしえないままで推定されることになる民間最終消費支出の推定値ではあるが、それは、当然のことながら、最終需要総額(第65式、第66式)のなかでは、最大の構成項目であり、最終需要総額の推定値の推移を決定する最重要な要素となる。
この最終需要の推定値は鉱工業生産指数(第87式)や第3次産業活動指数(第89式)を決定し、ひいては全産業活動指数(第92式)を決定する。これらの第87式や第89式も、多元回帰推定によったstochastic な関数であるが、やはり、変化率関数ではないので、外生的な衝撃から生じる波動的な変動をフォローしうるような能力は乏しい。とくに、この鉱工業生産指数(第87式)という内生変数についてのファイナル・テストの結果のグラフを見てみると、その結果があまり良くはなく、とりわけ波動追跡能力の弱さが(とくにデータ観察期間の後半について)明らかに観察されうる(もちろん、これは、第1式の民間最終消費支出関数からの推定誤差が累積してきているからでもある)。
にもかかわらず、この「日経モデル」で、非常に重要な役割を演じているのが、まさに、この第87式という関数で決定される鉱工業生産指数の推定値であって、これが企業資本設備の稼働率を決め(第88式)、それが、失業率ならびに求人倍率を決定し(第99式、第102式)、さらに、それによって就業者数も決まる( 第101式)という形になっている。労働時間数の決定(第103式、第104式)においても、鉱工業生産指数の推定値は、全産業活動指数(第92式:定義式)を介して大きな影響力を持つという体系になっている。また、上記のごとく、鉱工業生産指数の推定値から決定さる企業資本設備の稼働率の動きが企業の経常利益(第30式)をも決め、それが、春闘の賃上げ率を決める(第116式)という形にもなっている。これが、上記のごとく、やはり、鉱工業生産指数の推定値によって決まってきたと言ってよい就業者数(第101式)ならびに労働時間数(第103式、第104式)の推定値とともに雇用者報酬額(第120式:定義式)を決定し、それが主となって、家計の可処分所得の推定値が決まる(第123式)ということになっているのである。
そして、上述のごとく、この家計の可処分所得の値は、民間消費支出関数(第1式)における説明変数であるから、第123式で算定された家計可処分所得の推定値は第1式の民間消費関数にフィードバックの形でインプットされ、モデルは走っていくことになるわけである。ただし、このようにループ型の因果連鎖が構成されてはいるものの、家計の可処分所得(第123式)の推定値が、先決内生変数として、次期の民間消費支出を算定するために第1式にインプットされるという完全なリカーシブ型のモデルにはなりきっておらず、同時決定型 simultaneous の体系のままとされている。
以上の解説で明らかなごとく、「日経モデル」では、変化率関数ではないために最終需要の変化に対する反応が鈍感であるうえに、先決内生諸変数からのタイム・ラッグによる拘束を受けて、いわば「過去からの惰性」で被説明変数が決まるという性格を持っている民間最終消費支出関数(第1式)の推定値が、同じく変化率関数ではないところの(したがって感応性が余り敏感ではないところの)鉱工業生産指数関数(第87式)の推定値を縛り、それが、やはり同様に変化率関数ではない関数で決定される幾つもの内政変数を、かなり遠回りの連鎖を通じて決定していくことになる。そして、そのような連鎖のあげくに、家計の可処分所得(第123式)の推定値が決まり、ようやく、それが、民間最終消費支出関数(第1式)にフィードバック(ただし、同時決定的に)されるわけであるから、最終需要の自生的な変化に対する感応度が鈍く、しかも、過去からの惰性に拘束されて決まるという傾向が、そのような因果連鎖を通じて、いわば悪循環を形成し、それが、ほとんど是正されえずに持続することにならざるをえないはずである。
そうである以上は、実験的にたとえば公的投資(すなわち公共投資)を一定の額だけ増やすといった外生的な衝撃を与えてモデルにランさせるといったシミュレーションを行なってみた場合にも、それによって計測された乗数値が、わずかに1.5といった小さな値にしかならず、しかも、それが、ほとんどそのままの値で長期間にわたって続いてしまうというような算定となり、実際のGDP勘定の諸数値との整合性が保たれていないという結果になるのは、いわば必然なのである(乗数値が2.5程度の値でなければ、年額500兆円という近年の実際のGDP額を整合的に裏付けて説明することが不可能になる)。すなわち、「日経モデル」は、外生諸変数をすべて現実値のままとしてランをさせる「ファイナル・テスト」の場合は、諸内政変数が、それらの実際値をかなりフォローしえるとしても、ここで述べた「乗数テスト」のようなショック・テスト的なシミュレーションを行なってみた場合には、重要な内生変数の幾つかについてのモデル推定結果が、理論的に正常値と見なされうるような範囲から逸脱してしまい、それに復帰しえないというモデル特性を示してしまったということなのである。
なお、第1式では、上述のように、タイム・ラッグ付きの被説明変数それ自体が説明変数の一つとして用いられているのであるが、このような場合には、通常のダービン=ワトソン検定では誤差項の自己相関の有無(もちろん、有ってはならない)のチェックが不十分になる。このような形の関数の場合には、「ダービンのh検定」にかけてみる必要があるのであるが、「日経モデル」では、それが行なわれたかどうかを、確かめておくべきであろう。
実は、この「日経モデル」における上記で解説したような諸内生変数のモデル推定値を決定する因果連鎖には、このモデルに組み込まれている生産関数との関連で、「過剰決定」という重大な欠陥が含まれている疑いもある。この点については、以下、生産関数の問題とのかかわりで、コメントすることにしたい。
生産関数、デフレ・ギャップ、および、過剰決定の諸問題
この「日経モデル」では、生産関数は、コッブ=ダグラス型の関数を、よく行なわれるように、「労働の資本装備率」が「実質労働生産性」を決定するという形の関数に変形して推定(季節変動を除いたデータへの回帰推定)した結果として示されている(第84式:この関数も変化率型の関数ではない)。周知のごとく、この場合、説明変数である「労働の資本装備率」について推計されたパラメーター(すなわち回帰係数)は、実際のGDP勘定における「資本への分配率」の値と一致(近似)しなければならない。ところが、この第84式に示されている該当のパラメーターの値は0.2781であり、90年代のわが国のGDP勘定における「資本への分配率」の実際値0.42 〜 0.46 とは大きく食い違ってしまっていて、まったく整合的ではない。これでは、このモデルを用いた諸種のシミュレーションで、数多くのミス・リーディングな算定結果を生じることになるのは、避けられないところであろう。
このような不整合的な関数推定結果が生じる原因としては、データ面での問題(とくに、稼働率データの信頼度不足)や、推定理論で言うところの「多重共線性」multicollinearity の作用などが考えられるが、いずれにせよ、このような場合には、筆者(丹羽)がずっと以前から指摘し提唱してきたように、stochastic に推定された生産関数を用いることを断念し、GDP勘定から得られる実際の「資本への分配率」の数値をア・プリオリに適用した「理論的に確定された生産関数」を用いるように、モデル・ビルディングの手法を改めるべきである(近年では、旧経済企画庁や現在の内閣府も、「経済白書」や「経済財政白書」で、生産関数については、一応、このようなやり方を用いるように改めている)。
また、この「日経モデル」では、「GDPギャップ率」(すなわち「デフレ・ギャップ率」)として算式(定義式)が示されているのは、このモデルの第86式であるが、その意味するところも、まことに奇妙である。すなわち、この「日経モデル」では、上記の生産関数(第84式)に企業資本設備の「平均的な稼働率」と「平均的な労働就業率」と「平均的な労働時間」などをインプットして「平均的な実質GDP額」算定し、それを「潜在GDP額」であると見なしたうえで(これは、上記の第84式の「変換後」の型として同式と同じ箇所に示されている)、そのすぐ後に示されている第86式では、この平均的な「潜在GDP額」(GDPCAP95@という変数名が用いられている)を、上記の第84式の生産関数から計算される各期の実質GDP額推定値(GDP95@という変数名)から差し引いた残差を「GDPギ ャップ」であると、定義しているのである。
もともと、第84式の生産関数は、変化率型の関数ではないから、波動をフォローする能力は乏しく、したがって、この生産関数は、いわば、上下への波動をならした平均的な趨勢をフォローしていくような特性をもった関数である。それを、さらにいっそう平らにならした「平均的なGDP額」を求めたものが上記の「潜在GDP額」と呼称されている数値系列である。したがって、この両者のあいだの差額は、きわめて僅かなものでしかないはずであり、そのような意味のものとして定義・算定される「GDPギャップ」の額は、極度に小さな額になってしまうことになる。このようなわけで、この「日経モデル」では、近年ないし現在のわが国の経済における「GDPギャップ率」すなわち「デフレ・ギャップ率」は、常に、ネグリジブルと見なしうるほどの僅少なものでしかないという算定結果が、示され続けることにならざるをえない。こ
れは、まさに、非現実的かつミス・リーディングな欺瞞情報の極致であると、言わねばならない。
そもそも、「デフレ・ギャップ」(すなわち「GDPギャップ」)とは、完全雇用・完全操業の状態が達成されたと仮定した場合に形成されうるはずの実質GDP水準という「真の意味」での「潜在実質GDP額」(いわば「天井」の水準)に比べて、現実の実質GDP額の水準が、どれだけ下回ってギャップを生じているかを言うのである。したがって、たとえ生産関数を用いて計算したものであろうとも、「平均的な実質GDP額」の水準からの各期のGDP水準の偏差という意味に「デフレ・ギャップ」(GDPギャップ」の意味を定義するということは、きわめて大きな誤りであり、端的に言えば、きわめて悪質な「すり替え的」曲解である。確かに、1990年代を通じて、旧経済企画庁は、そのような「すり替え的」曲解による計算結果を「経済白書」などに示し続けてきたのであるが、しかし、その旧経済企画庁も、平成十二年版の「経済白書」では、そのような概念上の誤りを気にしはじめたかのごとく、若干は、それについての弁解的な記述を行なっているのである。そして、旧経済企画庁を平成十三年より吸収・統合した内閣府の「経済財政白書」(平成十三年版)では、少なくとも「GDPギャップ」(デフレ・ギャップ)のコンセプトそれ自体に関しては、このような誤りは是正されたのである(ただし、計算の面では、内閣府も、諸種のトリック的な小細工を弄して、旧経済企画庁の行なったものとほとんど同じ結果が算出されるようにしてしまっている)。
ただし、旧経済企画庁の「経済白書」であってさえも、上記の「日経モデル」の第86式に示されているような奇妙きわまる「GDPギャップ」のコンセプトまでは用いていない。上述のごとく、「日経モデル」の第86式では、生産関数で計算される「平均的な実質GDP額」(「潜在GDP額」と称されている)の推定値と、同じく生産関数で算定される「毎期の実質GDP推定値」とのあいだの差額を求めて、それを「GDPギャップ」だとしているのであるが、旧経済企画庁のやり方は、それとは違う。旧経済企画庁のやり方は、総需要で決まる毎期の「実際の実質GDP額」と「平均的なGDP額」の差を「GDPギャップ」だとして、示したのである。
このような旧経済企画庁のやり方を踏襲するとしたら、「日経モデル」の場合はどうなるであろうか? もちろん、モデルをランさせるのであるから、毎期の「実際の総需要」で決まる実際の「実質GDP額」を使うのではなくて、その代わりに、毎期における各最終(有効)需要項目のモデル推定値の合計額(すなわち「総需要」のモデル推定額)として定義式で算定される「実質最終需要額」(すなわち支出面から把握された実質GDP=実質国内総支出)の「モデル推定値」を使うことになるはずである。これは、上掲の因果連鎖図にもあるように、この「日経モデル」の第65式として示されているものである。これと、上記の第84式の生産関数の「変換後」の形として示された平均値的な趨勢線の値である「潜在GDP額」との差が、旧経済企画庁が1990年代に「経済白書」で用いていた「GDPギャップ」と、ほぼ等しい概念の数値指標となるわけである。ところが、上述のごとく、「日経NEEDS」モデルでは、このような旧経済企画庁の算定方式さえ用いていないわけである。
しかし、ここまで考察を進めてくれば、自ずと明らかになるように、この「日経モデル」には、「実質GDP」という同一の内生変数について、その推定値決定のメカニズムを異にする二つの式(第84式と第65式)が組み込まれていることがわかる(第65式の「支出面から把握された実質GDP額」は、この式のままでは季節変動を除去した値のものではないとされているが、言うまでもなく、季節変動除去の公式(所与)の適用は、何の問題もなく、簡単かつ斉一的・機械的になしうるはずである。
このことは、きわめて重大な問題点がこのモデルには含まれていることを意味している。すなわち、上掲の因果連鎖の図が示すように、この「日経モデル」では「最終需要=国内総支出(すなわち支出面から把握されたGDP)」(第65式)からの因果連鎖で企業資本設備の稼働率や労働の就業者数や労働時間のモデル推定値が決まることになっているのであるが(第88式、第101式、103式、104式、等々)、当然、それらの数値は第84式の生産関数にインプットされて毎期の 実質GDP額(ただし、「平均・潜在実質GDP額」ではない「毎期の実質GDP額」)のモデル推定値が算出されることになる、しかし、その値は、第65式で総需要それ自体から算出されている実質GDP額のモデル推定値とは一致しない。また、イタレーション(繰り返し計算)を行なったとしても、この両者を一致させていくように働くようなフィードバック回路などは、このモデルには組み込まれてはいない。すなわち、この「日経モデル」には、「実質GDP額」という最も重要な内生変数について、過剰決定という致命的な欠陥が内含されているわけである。
この重大欠点を避けようと思うならば、第65式で支出面から決まる実質GDP額のモデル推定値を、第84式の生産関数にインプットして、いわば生産関数からの逆算の形で、その実質GDP額の形成のために必要とされるはずの資本と労働の投入量のモデル推定値を算定し、それに基づいて、企業資本設備の「稼働率」か、あるいは、総労働時間に換算された「労働投入量」の推定値を算定するというようなやり方をする必要がある。当然、そうなると、上掲の図の因果連鎖フローは変更されねばならなくなり、図に示されている方程式のうちの一本が、外されねばならなくなるであろう。このようなモデルの変更は、それほど困難なことではないであろうが、それによって、モデルの性格が、かなり変わってくることにはなろう。いずれにせよ、現在の「日経モデル」においては、このような対策は講じられてはおらず、過剰決定という重大な欠陥を持ったままにされているのである。
需給メカニズムによる物価決定プロセスの欠如
周知のごとく、価格というものは、需給関係で決まるものである。これを、マクロ・ベースで表現すれば、
物価上昇率(%) = 総需要(名目額)の伸び率(%) ― 財の供給量の伸び率(%)
である。もちろん、この式は、単なる「定義式」として解釈されてはならない。この式は、需要の伸びに応じて、企業が、いかに商品の生産・供給量を伸ばしうるかということによって、物価の動きが決まるということが、表現されているのである。これこそが、物価決定の基本原理である。
ところが、この「日経モデル」では、卸売物価指数、GDPデフレーター、消費者物価指数、等々、数多くの物価指標を、それぞれ決定・予測するための多数の方程式が組み込まれてはいるものの、それらは、全て、過去の趨勢からの惰性と、賃上げ率や労働分配率、輸入品価格の変動率などからもたらされるコスト要因の変動の影響のみによって物価の動きを説明しようとしている方程式ばかりである。しかし、最も基本的で不可欠であるはずの、上記の需給関係から決まる物価決定メカニズムは、まったく組み込まれてはいないのである。したがって、この「日経モデル」では、生産能力の余裕という意味のデフレ・ギャップ(GDPギャップ)の存在あるいは不存在、ないし、その大小ということが、物価動向にまったく影響を与えないというモデル構造になってしまっているのであり、きわめて奇妙かつ非現実的である。このことも、また、この「日経モデル」の、きわめて重大な欠陥であろう。
需給関係の問題については、まず認識しておくべきことは、近年ならびに現在のわが国の経済においては、GDPに占める在庫変動額のウェートが0.1 〜 0.4 パーセントにすぎず、ネグリジブルであるということである。つまり、需給がみごとに均衡しており、ミス・マッチなども、ほとんど生じてはいないというわけなのである。すなわち、現在、わが国の企業は、需要の変動に対応して、きわめて敏速・的確に諸商品を生産・供給しえているということなのである。この意味で、わが国の市場メカニズムは、きわめて優れたパーフォーマンスを示してきていると言わねばならない。すなわち、わが国の経済は、現在、ほぼ完璧な需給均衡の状態にあるわけである。
マクロ経済学的な用語を用いて言えば、現在の日本経済は、まさに、「ケインジアン・クロス点」に位置しているわけであり、したがって、「需給ギャップ」はゼロと見なしてよいわけである。しかし、言うまでもなく、総需要の水準が低すぎるために、この「ケインジアン・クロス点」それ自体は、完全雇用・完全操業に対応した潜在GDPの可能上限という「天井」から見れば、ずっと低い水準のところにあり、したがって、巨大なデフレ・ギャップが発生し、居座っているわけである。筆者(丹羽)がオーソドックスな生産関数理論に基づいた成長会計分析の手法で精密に計測してみたところでは、本ホームページの英文論文に示されているように、現在のわが国の経済では、「天井」の実質水準から見て、現実の実質GDPの水準は6割程度の水準にとどまっている。すなわち、デフレ・ギャップが40パーセントも生じていると判定しなければならないのである(筆者丹羽は、この計測結果と、それについての厳密な吟味的考察を、2002年の11月30日 〜 12月1日 に日本経済政策学会が東京で開催した国際学会において、報告した)。「オーカンの法則」を用いた簡略計算法によっても、ほぼ同様な計算結果が算出されうる(『自由』誌、2003年5月号の丹羽論文参照)。要するに、現在の日本経済においては、「需給ギャップ」はゼロと見なしうるほどにネグリジブルなのであるが、本当の意味での「デフレ・ギャップ(GDPギャップ)」は、きわめて膨大に発生しているのである。残念ながら、「日経モデル」は、このことを把握し、計測・分析しうるようなモデル構造にはなってはいない。
言うまでもなく、巨大なデフレ・ギャップが生じているということは、生産能力の余裕がきわめて大きいということを意味している。したがって、デフレ・ギャップが膨大に生じている現在の日本経済においては、総需要が大幅かつ急速に増やされたとしても、なにしろ生産能力の余裕がきわめて大きいわけであるから、需要の伸びに応じて、なんらの問題もなく、諸商品の生産・供給もどんどん増やされうる。したがって、幾年かのあいだは、物価の上昇なしに高度経済成長が実現されうることになる。しかし、そのような幾年かの後、デフレ・ギャップがほぼ消失し、実質GDPの水準が完全雇用・完全操業の「天井」に達した状態になったときに、この「天井」の勾配(=潜在成長率)を上回って総需要が増やされると、諸商品の生産・供給が需要に追いつかなくなり、インフレ・ギャップが生じ、それに応じて物価の上昇が起こりはじめる。このように、デフレ・ギャップが生じているときと、インフレ・ギャップが発生したときとでは、それに応じる諸商品の生産・供給の推移や物価の動向は、対照的に異なる。「日経モデル」が、このことの計測・分析を行ないえないようなモデル構造になってしまっていることは、このモデルによる分析が、わが国の今後の経済政策のあり方についての指針とはなりえないようなミス・リーディングなものとならざるをえないであろうということを、意味しているわけである。筆者(丹羽)は、このことを、まことに残念に思い、また、憂慮しているしだいである。
以上のような筆者によるコメントは、「日経NEEDSモデル」を誹謗しようというような意図で述べたわけでは、けっしてない。筆者は、日本経済新聞社サイドから、要望がありさえすれば、「日経NEEDSモデル」の上記のような問題点を是正し、改善するために、損得を度外視して、いくらでも協力する所存である。皆で力を合わせて、そのように、「日経NEEDSモデル」を改善することが、日本経済を立ち直らせるためにも、ぜひとも必要なことだと、筆者は考えているしだいである。
「日経NEEDSモデル」(MACROQ60)は、方程式数が二百数十本にも達する計量モデルである。したがって、その全部について詳細に吟味してコメントするといったことは、あまりにも煩雑な作業になってしまう。そこで、本稿では、この「日経モデル」の最も重要な中核と思われる部分のみを取り上げて、吟味するにとどめた。
(平成15年6月20日、丹羽春喜 記)
論 文
- 1.政策要求書 : 政策要求書本文、詳論および別表(平成10年9月)
- 2.建白書 : 小泉首相あて建白書「打ち出の小槌」を振る決断を!(平成14年1月)
- 3.建白書への補論 : 政府貨幣と日銀券の本質的な違い(平成14年1月)
- 4.日本経済政策学会 :日本経済政策学会共通論題セッション丹羽報告(平成10年5月)
- 5.Deflationary Gap:東アジア経済学会第6回世界大会丹羽報告(平成10年8月)
- 6.スティグリッツ提案弁護 : スティグリッツ氏の提案は間違ってはいない(平成15年7月)
- 7.日経モデルの問題点 : 日経モデルの問題点(平成15年6月)
- 8.特別論説: ルーカス型総供給方程式の一般化(詳論)(平成13年9月)(pdf:219KB)
- 9.Deflation Gap : -続-デフレ・ギャップ計測−続(平成14年 12月)
Abstract(要約)(pdf:22.2KB) 本文(pdf:585KB)
- 10.政策提言(平成18年秋 ):簡潔明瞭でインパクトのある政策案マニフェスト提案
- 11.危険! 19年度国家財政 :新年度のわが国家財政危うし(『月刊日本』19年2月号)
- 12.重要国策の遂行は絶望 :
マクロ経済学という科学を捨てては重要国策の遂行は不可能(『自由』19年6月号)
- 13.新古典派は市場原理否認:新古典派「反ケインズ主義」は市場原理を尊重していない(『自由』19年7月号)
- 14.「内閣府推計批判」:「内閣府の需給ギャップ推計値は誤りと欺瞞の極致だ!」(「月刊日本」平成19年9月号)
- 15.巨大地震活動期に備えるマクロ政策体系の構築 -「第3の財政財源」確立の方法論を中心に-
- 16.有効需要に生産は即応しうる― 周知の「過剰決定」問題解決として(詳論)
- 17.2013年ケインズ学会大会報告論文
Abstract(要約)(pdf:22.2KB) 本文(pdf:585KB)
