重要国策の遂行は絶望
マクロ経済学という科学を捨てては重要国策の遂行は不可能
『自由』平成19年6月号
日本経済再生政策提言フォーラム会長
経済学博士 丹羽春喜
戦前の米国で超大軍拡を可能にしたもの
戦前の米国では、1930年代の大不況期の約10年間に生じた巨大なデフレ・ギャップによって、合計5000億ドルないし1兆ドルの潜在実質GNP(1929年価格評価)を失ったと見積もられています(ラーナー著『雇用の経済学』第3章)。
その年の秋、ウォール街株式市場の暴落が大恐慌勃発の契機となったことで知られている1929年において、米国のGNP水準は1040億ドルでした。大不況が最もひどかった1933年ごろには、実質タームでそれが3割減の700億ドル(同じく1929年価格評価)となり、名目値ではもっと低くなりました。 その後、ルーズベルト政権のニュー・ディール政策でかなり上向いたとはいえ、30年代末でも、米国の実質GNP水準は29年の水準を、やっと回復することができたか、できなかったか、といったところに達しえていたに過ぎませんでした。すなわち、当時の米国経済は、あの10年間におよぶ大不況での巨大なデフレ・ギャップの発生という形で、1929年ごろの年間実質GNP額(あるいは、それとほぼ同水準であったと思われる1930年代末ごろの年間実質GNP額)との対比で言えば、その5倍ないし10倍、そして、1933年ごろの年間実質GNP額との対比では、その7倍ないし14倍にも達するほどの合計額の潜在実質GNPを失ってしまっていたのです。
しかし、重要なことは、ニュー・ディール政策時代の後半ともなると、米国の政策立案ブレーンたちのあいだでは、このような当時の米国経済における、デフレ・ギャップが厖大であることについての、すなわち、観点を変えれば、マクロ的生産能力に巨大な余裕が存在していることについての、かなり正確な認識がひろく持たれ始めていたということです。このことが、当時のわが国にとって、いかに重大な意味を持っていたかということは、以下のような戦前の史実を想起してみれば、明らかなところでしょう。
わが国は、1937年(昭和12年)を期してワシントン軍縮条約の継続拒否・廃棄を行なうこと決断し、同条約の規定に基づいて1934年(昭和9年)の12月に米英等にそれを事前通告しました。さらに、高橋是清蔵相が2・26事件で難にあった年である1936年(昭和11年)の1月には、ロンドン軍縮条約からの脱退をも同様に事前通告しました。これによって、1937年(昭和12年)からは、いわゆる「無条約時代」の幕開けとなったわけですが、わが国は、こうすることによって、両条約で6割という劣勢比率に抑え込まれていたわが海軍力の対米比率を、7割ないし8割程度にまでは高めうると、期待したのです。
ところが、米国は、「待ってました!」とばかりに、第1次、第2次、第3次ヴィンソン案、さらには、スターク案といった想像を絶して厖大な海軍軍備の急速な大拡張計画を策定・実施しはじめ、わが国にとっては、深刻な危機的事態の到来を意味するような情勢の推移となってしまいました。
つまり、米国では、1930年代の半ばも過ぎた当時になると、すでに、多くの政策担当者たちに、ケインズ理論がよく理解されるようになってきており、それにともなって、デフレ・ギャップのコンセプトも明らかにされ、また、その規模の推計・計測も、かなり行なわれはじめていたのです。すなわち、米国政府が、「無条約時代」を迎えて、そのような超厖大な軍拡計画の策定・実施に踏み切ることができたのは、当時の米国経済におけるマクロ的な生産能力の余裕であるデフレ・ギャップが、上述のごとく、きわめて巨大であったということを、米国の当時の政策担当者たちが、かなり、よく知るようになってきていたという事情に、大きく助けられていたのです。そして、そのような軍備の大拡張と、それに続く巨額の戦費支出が行なわれはじめると、米国の実質GNPは、瞬く間に倍増したのでした。
しがって、そのようなケインズ経済学の理論やデフレ・ギャップのコンセプトについての知識が、まだ、米国政府当局にも無かった1920年代や30年代当初の頃に軍縮条約の破棄が行なわれていたとすれば、米国といえども、あれほどまでに厖大な軍拡案を策定するなどということは、思いもよらないことであったと思われます。この意味で、わが国によるワシントン、ロンドン両軍縮条約の破棄通告にともなう「無条約時代」の開始が、まさにケインズ的政策の開花期が始まったのと期を一にして、1937年(昭和12年)となってしまったことは、わが国にとって、まことに悪いタイミングであったと言わねばなりません。
しかも、わが国では、ケインズの主著『雇用、利子、貨幣の一般理論』の公刊(1936年)による「ケインズの有効需要政策の理論」の確立に数年も先立って「事実上の模範的ケインズ的政策」を実施して優れた成果をあげた高橋是清蔵相が、2・26事件で非命に倒れた後の1930年代の末ないし1940年代前半においても、まだ、デフレ・ギャップの概念やそれを推計・計測する手法などは、あまり知られてはいなかったのです。1941年(昭和16年)12月8日の対米英「大東亜戦争」開戦が、わが国にとってきわめて悲劇的なものとならざるをえなかった一つの大きな要因が、ここに潜んでいたわけです。
過去四半世紀5000兆円の潜在GDP喪失
私(丹羽)が、本誌においても、厳密な経済理論に基づく実証的計測の結果を示しつつ繰り返し指摘してきたことですが、わが国の経済において発生・累増してきたデフレ・ギャップ(現在のわが国では「GDPギャップ」とも呼称されている)は、きわめて厖大です。本稿でも、ここで、1970〜2005年の期間についての、わが国経済におけるデフレ・ギャップの発生・累増状況を計測した主要な算定結果をグラフとしてまとめて、第1図として掲げておきます。この第1図では、「完全雇用・完全操業」(企業資本設備と労働力人口を総合して97%の稼動率に達した場合を、事実上の完全雇用・完全操業であるとしました)の状態を想定した場合の潜在実質GDPが、(高)(中)(低)の3系列として、いわば幅を持たせて推計されていますが、(中)の系列の推計値で見てみましても、2005年(平成17年)の潜在実質GDPは936兆円(1990年価格評価の実質値)と算定されています。同年の実質GDPの実際値は、その5割6分にすぎない520兆円(同じく1990年価格評価)にとどまっていました。すなわち、44パーセントものデフレ・ギャップの存在が実証的に示されているわけであり、わが国の経済からは、最近年においても、年々、400兆円あまりの潜在実質GDPが、実現されえずに空しく失われていっているのが現状なのです。この第1図を一瞥しただけでも、およそのところは目算しうるように、わが国の経済においては、過去四半世紀(ないし30年間ほど)のあいだに、累増し巨大化し続けてきたデフレ・ギャップという形で失われた潜在実質GDPの総額は、5000兆円(1990年価格評価の実質値)にも達します。近年のわが国のGDPの実際値が年額500兆円あまりの規模ですから、その約10倍近くもの潜在実質GDPが、生産能力の余裕が十分にあったにもかかわらず、総需要の不足のゆえにそれが実現されることができず、わが国の経済社会から空しく失われてしまったのです。これは、まさに、言語に絶する大惨害であったわけです。
近年の年間GDP額の約10倍もの巨額の潜在実質GDP額が、過去四半世紀のわが国の経済から失われてしまったと言われると、その厖大さに、「にわかには信じ難い」と思われる読者も居られるかもしれません。しかし、上述のごとく、戦前の米国も、1930年代の大不況期の約10年間にわたって生じた巨大なデフレ・ギャップによって、1929年の年間実質GNP額の、あるいは、それとほぼ同水準にようやく回復しえた1930年代末ごろの年間実質GNP額の、5倍ないし10倍、不況が最も激しかった1933年ごろの年間実質GNP額との対比では、その7倍ないし14倍にも達するほどの合計額の潜在実質GNPを失ったのですから、上記の過去四半世紀(ないし30年間)のわが国で失われた潜在実質GDP総額の見積もり額は、けっして過大推計といったものではなく、むしろ、控え目な推計値であると考えられるべきでしょう(GNPもGDPも、ともに、減価償却額をも含めたグロス・タームでの国民所得額を示す類似概念ですから、両者の数値のあいだには、それほど大きな差異はありません)。
需給ギャップとデフレ・ギャップ
過去十数年というものは、 わが政府当局(旧経済企画庁および現内閣府)は、このようなわが国の経済における厖大なデフレ・ギャップの発生・累増の状況を正しく計測することを怠り、その実情を隠蔽・秘匿し、あるいは、欺瞞し続けてきました(このことについては、丹羽の著書『新正統派ケインズ政策論の基礎』、学術出版会、平成18年刊において、詳細・厳密に論述されています)。マスコミも、それに追随してきました。そのような状況にともなって、わが国においては、官庁エコノミストたちのみならず、ひろく、経済問題に関する論壇においても、また、関係学界においても、ミス・リーディングな迷論が横行するようになってしまっています。
その典型的なケースとしては、たとえば、「需給ギャップ」という概念が不明確をきわめているのが、今では、むしろ、一般的な状況であるということに表れています。景気の回復を物語る指標として、「今や需給ギャップが消失した!」とか、「むしろ需要超過になっている!」といったことが、内閣府などから、再三再四、公表され、マスコミも、それを肯定的に大きく報道しているのが、最近のわが国の状況です。しかし、そもそも、その場合の「需給ギャップ」とは、何を意味しているのであるか?「デフレ・ギャップ」(ないし「GDPギャップ」)と同じ意味なのか?別個の概念なのか? そういった最も基本的かつ初歩的なことが、プロのエコノミストたちにも、さっぱりわからなくなってしまっているのが、わが国の現状なのです。
マクロ的に経済全体で諸商品の需給が均衡しているかどうかの本当のところを見るには、GDP(ないしGNP )に占める在庫変動額の比率をチェックすればよいのです。近年のわが国においては、毎年のGDPに占める在庫変動額の比率は、きわめて微少であって、0.3〜0.6パーセント程度でしかありません。ということは、わが国の経済では、企業部門が需要の変動に応じてきわめて敏速・的確に諸商品を生産・供給しており、諸商品の売れ残りによる在庫増加や、その逆の供給不足による在庫の減少が、ともにネグリジブル(無視しうるほど僅か)でしかないということです。すなわち、この点では、近年のわが国の市場メカニズムの効率は非常に良く、マクロ的に需給は均衡していて「需給ギャップ」がほとんど生じていないという意味での「マクロ均衡」の状態が、続いてきているわけです。
しかし、第1図に示されているように、近年のわが国経済では、そのようにマクロ的に需給が均衡しているにもかかわらず、巨大なデフレ・ギャップが発生・累増し、居座っているということも確かです。すなわち、近年のわが国の経済では、「需給ギャップ」はほとんど生じていませんが、しかし、「デフレ・ギャップ」は大規模に存在しているのです。このことは、やや逆説的に感じられることであるかもしれませんが、実は、経済理論的にはごく簡単に説明しうるような、ありふれた現象にすぎません。このことを、読者諸氏の多くも学生時代に経済学の初級コースで学ばれたはずの有名な「45度線モデル」の図解を用いて、下記のごとく、平易に説明しておきましょう。
第2図を見てください。近年のわが国の経済では、マクロ的に需給が均衡しているのですから、その均衡点は(タテ軸で測った総支出とヨコ軸で測った総生産・総供給が等しいところの)45度線上のたとえばQ0点(ケインジアン・クロス点と呼ばれています)として示すことができます。それに照応しているGDPはY0です。しかし、このQ 0点は、完全雇用・完全操業の「フル・キャパシティー稼動」状態での潜在GDPであるY(ー)に対応したマクロ均衡点Q(ー)よりは、ずっと低いところに位置しています。この両均衡点の高さの差、すなわち、ヨコ軸のGDPで測った場にはY(ー)とY0とのあいだの距離がデフレ・ギャップ(GDPギャップとも言う)です。
言うまでもなく、このデフレ・ギャップは、マクロ的な生産能力の遊休ないし余裕であると解釈することができるわけです。すなわち、近年のわが国では、経済が、ほぼ、マクロ均衡点(ケインジアン・クロス点)に在るため、需給が均衡しており、「需給ギャップ」は無いと言ってもよいでしょう。しかし、第2図のY(ー)とY0とのあいだの距離として示されているような「デフレ・ギャップ」は、第1図のごとく、わが国の経済においては、1970年代の後半より現在まで、長期的かつ厖大に、発生・累増してきているのです(戦後の今になって計測してみますと、戦前の1930年代のわが国の経済でも、デフレ・ギャップがかなり大きく発生していたことがわかりましたので、本誌の平成16年10月号の丹羽論文で、そのことを論述しておきました)。
デフレ概念の曲解
「デフレ」という経済用語は、かなり、意味があいまいです。しかし、従来からの最も一般的な慣行としては、「金融収縮や総需要の低下・低迷といったデフレーション過程にともなって発生した不況」という意味での「デフレ不況」を表す語として用いられてきたと言ってよいでしょう。そして、そのような「デフレ不況」の現象が生じているような場合には、必ずデフレ・ギャップが発生しているのです。
ところが、最近のわが国においては、政府当局が、上掲の第1図に示したようなデフレ・ギャップの実情を計測・公表することを怠っているばかりか、むしろ、それを隠蔽・秘匿してきているような状況であり、それにともなって、第2図に示されたような経済理論的に正しい意味でのデフレ・ギャップ概念も、顧みられなくなってしまっているのが実情です。そのことの一つの随伴現象として、「デフレ」という用語を「物価の下落」という意味にのみ解して、物価の下落が止まってその上昇が始まることをもって「デフレ脱却」だとし、それを政策効果をも含む経済の成績(パーフォーマンス)の判断基準としているといったスタンスが、非常に広く見られるようになってしまっています。
言うまでもなく、これは、はなはだしくミス・リーディングかつ誤謬に満ちたスタンスです。なぜならば、たとえば、わが国でも幾度か経験されたような、原油など原・燃料の輸入価格の高騰といった要因から生じるコスト・プッシュ型(コストから押し上げる型)の物価上昇は、不況下でも生じうるわけですが、そのような、いわゆる「スタグフレーション」の状態となれば、それは経済の状況をいっそう悪化させるものにほかならないわけですから、それを、物価が上昇したからといって、「デフレからの脱却」がなされたなどと、あたかも「良いこと」であるかのごとく判定するといったことは、大きな間違いであるからです。
一昨年から昨年にかけての原油価格の高騰の結果としてわが国でも生じた一般物価の下げ止まりや企業物価の上昇は、明らかにコスト・プッシュ型の物価の動きであったと見るべきものでしたが、日銀や内閣府などの政策当局者たちは、それを、わが国の経済が「デフレからの脱却」を達成しつつある「良い兆候」であるかのごとく示唆してきました。マスコミも、ほぼ全面的に、それに追随してきました。すなわち、現在のわが国では、政策当局やマスコミが、ディマンド・プル型(需要が引っ張る型)の物価上昇と、コスト・プッシュ型の物価上昇との区別を行なわなくなってしまっているらしいのです。もちろん、このことも、わが国の経済にとって、ずいぶん危険なことです。なぜならば、このことだけからでも、政府の経済政策が過誤をおかしがちとなり、マスコミもそれに気がつかないといった状況が、頻々として起こることになりかねないからです。
このように、政策担当の経済官庁やマスコミのエコノミストたちが、ディマンド・プル型とコスト・プッシュ型という二種類の物価上昇を区別しなくなっているということは、とりもなおさず、彼ら(あるいは彼女ら)が、インフレ・ギャップとデフレ・ギャップの概念や特質を理解するということを、まったく怠ってしまっているということを意味しています。なぜならば、ディマンド・プル型の物価高騰はインフレ・ギャップが発生している場合にのみ生じうるのであり、デフレ・ギャップが発生している状態の下での物価上昇は、上記でもふれたように、コスト・プッシュのメカニズムによるものに限られているという重大なことが、無視されているからです。そして、彼ら(彼女ら)が、どうやら、マクロ経済学の最も基本的で初歩的な定理、すなわち、インフレ・ギャップとデフレ・ギャップがマクロ的に同時発生するなどということは、そもそも、ありえないことだという鉄則を、忘れてしまっているらしいということは、きわめて憂慮すべき重大な事態でありましょう。
「有効需要の原理」否認は誤り
デフレ・ギャップが発生するということは、言うまでもなく、いわゆる「総需要」すなわち「有効需要支出」(生産されたモノやサービスを実際に購入する支出)の総額が不足し低迷しているために、せっかくの生産能力(本源的には労働力と企業資本設備)が十分に活用されえない(したがって潜在GDPが空しく失われる)ということにほかなりません。したがって、デフレ・ギャップ(あるいはインフレ・ギャップ)の概念やその規模を顧慮しないということは、その当然の帰結として、「有効需要の原理」の否定というスタンスに行き着くことにならざるをえないわけです。
近年(および現在)において、わが国の経済政策当局ならびに官庁エコノミストたちの公式のスタンスも、ほかならぬ、この「有効需要の原理」の働きを否認し、フィスカル・ポリシーによる有効需要政策の有効性を認めることを拒否するということになってしまっているように思われます。小泉内閣の経済政策の基調が、まさに、それであったことは、ほぼ、間違いのないところでありました。そして、民間や学界のエコノミストたちの多くも、この大勢への追随をこととしているのが、現状であると言ってよいでしょう。
「有効需要の原理」は、近年の日本経済の具体的なパターンを例にとって説明してみると、よくわかります。すなわち、経済において、独立変数として作動して年々のGDPを創り出す基本的な指標となっている「自生的」(じせいてき、autonomous)な有効需要支出は、「民間投資支出額+純輸出額(すなわち財貨・サービスの貿易収支額)+政府(地方自治体をも含む)支出額」ですが、近年の日本経済においては、そのマクロ的なトータルは約200兆円(年額)です。それから発生する乗数効果を通じて、年々の「家計消費支出額」約300兆円(年額)が生み出され、その両者の合計として、周知のごとく、年額約500兆円(いずれも名目値ベース)のGDE(すなわち国内総支出)= GDP(国内総生産すなわち減価償却額をも含めたグロス・タームでの国民所得額)が形成されているのです。「有効需要の原理」は、このような明確なプロセスとして、常に作動・貫徹しているわけです。このように具体的に考えてみれば、「有効需要の原理」の働きを否認するなどということは、とうてい正気の沙汰とは思われません。にもかかわらず、近年(ならびに現在)のわが国政府の政策当局は、乗数効果がきわて微弱になってしまっているとして、上記のように、最近の日本経済では「有効需要の原理」は妥当しえなくなったとするスタンスに固執しているわけです。
上記の簡単な実際の金額を用いた説明で明らかなように、このところ、年々、約200兆円の「自生的有効需要支出」から、その2倍半の約500兆円のGDPが形成されているのですから、乗数効果の「ケインズ乗数値」は2.5前後であるはずです。これは、けっして小さな値ではありません。いずれにせよ、いま、政府筋のスタッフならびにそれに追随しているエコノミストやマスコミなどが想定しているような1.3以下といった小さな乗数値では、500兆円のGDPの形成は説明しえなくなるはずです。GDPの形成を説明しえないような経済分析は、失格でしょう。
ここで、付表を見てください。この表は、簡単な表ではありますが、きわめて重要なことを示しています。すなわち、この表は、わが国の経済について、1970年より2005年までの期間をとって、それを全体として眺めてみたり、あるいは、幾つかの期間に区切って観察したりしてみているのですが、その何れにおいても、トータルとしての「自生的有効需要支出額」の伸び率とGDPの伸び率とが、おどろくほどピッタリと一致しているのです。したがって、この表から直感的にわかることは、たとえば、3年、あるいは、5年といった期間に、トータルとしての「自生的有効需要支出額」が、年額で、かりに1.5倍、あるいは、2.0倍に伸ばされたとすれば、 GDPも同じく1.5倍、あるいは、2.0倍前後に伸びることが確実だということです。
つまり、現在のわが国の経済においては、トータルとしての「自生的有効需要支出額」の年々の額を増やしていきさえすれば、それと比例的にGDPをもきわめて確実に増やしていくことができるということなのです。しかも、「自生的有効需要支出額」の中では「政府支出額」が大きなシェアを占めているのですから、政府は、この「政府支出額」を適宜に増減させることによって「自生的有効需要支出額」をコントロールすることができるわけです。したがって、政府はGDPの成長をもコントロールすることができるはずなのです。しかも、デフレ・ギャップという生産能力のマクロ的余裕が巨大で、インフレ・ギャップ発生の怖れが現実的には皆無である現在の日本経済においては、後述するように、政府は「国(政府)の貨幣発行特権」という「打ち出の小槌」財源をタブー視する必要が無く、それをいくらでも活用しうるのですから、なおさらのことです。にもかかわらず、上記で指摘したように、過去四半世紀の期間に、わが国の経済から、合計5000兆円もの潜在実質GDPを空しく失わせてしまったということは、わが国の政策当局の弁解の余地の無い大失態であったと言わねばなりません。
要するに、現在の日本経済においては、「有効需要の原理」は、きわめて確実に作動し貫徹しているのです。私(丹羽)は、このことを、経済理論的にも、計量経済学的にも、きわめて厳密に吟味・確認する作業を行なったのですが、そのようなアカデミックな研究・分析によって得られた結論も、本稿に掲げたこの簡単な付表から上記のごとく直感的に読み取りとりうることを、疑念の余地無く裏書きするものにほかなりませんでした(上掲、丹羽著『新正統派ケインズ政策論の基礎』を参照)。すなわち、「有効需要の原理」の妥当性を否認するという当世風のスタンスは、まったく間違っているのです。
一個のサイエンスが葬り去られて
以上、本稿で指摘してきたような、過去四半世紀(とくに1990年代以降)における、わが国の政策当局とそれに追従する官庁・業界・学界のエコノミストたちやマスコミなどに通有の、合理性をいちじるしく欠如した混迷の極致ともいうべき経済思考パターンの数々は、要するに、ケインズ的なマクロ経済学の諸定理を、すべて否認・忘却しようとしているということなのです。ここで、一応、「ケインズ的な」マクロ経済学と記しましたが、本当は、そのような限定の句を付ける必要もないのです。なぜならば、それは、現代のマクロ経済学そのものの核心を構成しているところの、きわめて広い汎用性を持った疑念の余地の無い真理を体現している理論体系であって、複式簿記の原理で国民所得勘定(GDP勘定)の作成を行なっている社会会計学も、基本的には、このマクロ経済学の理論体系から導き出されているからです。ということは、本稿でも第2図で示したような「45度線モデル」を導き出す土台となっているマクロ均衡の方程式などを中心とするマクロ経済学の理論体系それ自体と、それに基づく財政政策・金融政策の政策理論体系が、現在のわが国では、ほとんど全面的に否定され、忘れ去られてしまおうとしているということなのです。すなわち、国家政策の立案・実施のためにも必須であるはずの、れっきとした一個のサイエンスが、全面的に葬り去られようとしているのですから、信じがたいような一大事です。本誌の読者諸氏は、「まさか!…‥」と思われるかもしれませんが、これが実情なのです。
言うまでもないことでしょうが、20世紀の後半以降、米国の思想界から発信されてきた「新古典派」経済学のイデオロギーを信奉する陣営は、あたかも、この世より「ケインズ的経済思想」を根絶しようとしているかのごとき強烈きわまりない「反ケインズ主義」の政治的思想攻勢を、グローバルに展開してきました(ただし、米国の連邦政府のマクロ経済政策のスタンスは、新古典派のそれに盲従しているわけではなく、明らかに、それと一線を画してきたようですが…‥)。近年のわが国政府の経済政策スタンスが、そのような「新古典派」イデオロギーの支配的影響を受けたものであったことは明らかなところです。とくに小泉政権では、それが顕著でした。上述のごとき、わが国の政策当局者やエコノミストたちの混迷状況も、そのことに由来していると思わねばならないわけです。
しかし、私(丹羽)が、本誌でも繰り返し平易に解説してきましたように、実は、米国流の「新古典派」経済理論なるものは、はなはだしく非現実的な仮定や欺瞞的な理論的トリックなどによって無理やりに構築された、きわめてニヒリスティックかつ無政府主義的な、まさに文明破壊的とも言うべき危険思想なのです。われわれ日本国民として、困惑せざるをえないことは、わが政府の経済政策スタンスが、そのような「新古典派」の「反ケインズ主義」イデオロギーの支配下にあるようでは、わが国の、破綻の危機にひんしている政府財政を再建し、経済を低迷状態より脱却させて力強い興隆軌道に乗せ、自然環境の改善や社会保障の充実を推進するとともに、なによりも、防衛力の整備・拡充を断行して、他国からの侵略やあなどりを受けることのないようにするといった重要国策の遂行が、ほとんど不可能になってしまうということです。なぜならば、このような重要国策の効果的な遂行のためには、なににもまして、経済政策当局によるマクロ経済理論の確固とした再確認と、それに基づいた大規模かつダイナミックなケインズ的政策の立案・実施ということが、必須であるからです。
言うまでもなく、そのような重要国策を遂行するにあたっては、わが国における物資やサービスのマクロ的な生産能力の余裕の有無や、その余裕の規模などを確認することが、まず必要です。すなわち、本稿の第1図として私(丹羽)自身の計測結果を示したようなデフレ・ギャップやインフレ・ギャップの正確で信頼度の高い測定が、常に、システマティックに行なわれて、それが政策立案に広く有効利用される必要があるのです。ですから、現在のように、わが政府当局がそれを怠り、むしろ、デフレ・ギャップの発生・累増の実情が政府によって隠蔽・秘匿されているような状況であって、わずかに、私(丹羽)のみがそのような計測作業を小規模に行なっているようなことでは、まことに心細いしだいです。政府が、いましばらくは、そのような無責任なスタンスを改めないというのであれば、それに代って、民間の有力な研究機関が、これに取り組むべく奮起していただきたいものです。
上記のような重要国策を推進するためには、相当に大規模な財政政策の実施が必要となるでありましょうが、第1図に示されたような厖大なデフレ・ギャップという形の巨大なマクロ的生産能力の余裕が存在している現状では、そのような財政政策のためのマネタリーな財源調達手段としては、国債発行や増税に頼るべきではなく、わが国の現行法でも認められている「国(政府)の貨幣発行特権」(seigniorage、セイニャーリッジ権限)という「打ち出の小槌」財源を、なんらかの形で大規模に活用するべきでしょう。今日では、経済社会における取引の大部分は多角的な電子決済で行なわれているのですから、財政政策がこの「打ち出の小槌」財源によって実施されるからといって、「紙幣を刷りまくる」必要などはありません。エコノミストであれば、誰でもが知っているように、現金通貨流通量は、GDPの増加額に「マーシャルのk」(マクロ・ベースの現金通貨流通速度の逆数)という0.08〜0.16程度の係数を乗じた額だけ増えるだけです。この「マーシャルのk」の値それ自体も、金融政策によって、ある程度は調節することができます。このような「打ち出の小槌」財源を活用する政策案を、私(丹羽)は、10年も前から繰り返し提言してきたわけで、本誌でも、そのような提言を繰り返し叫んできました。大多数の読者諸氏は、そのことを、よく知ってくださっていることと思います。
一刻も早く知的混迷からの覚醒を
ここで、いま一度、戦前のことを想起してみましょう。上述しましたように、米国では、1930年代の半ばも過ぎた頃からは、すでに、多くの政策担当者たちが、ケインズ理論、とくにデフレ・ギャップのコンセプトを、かなりよく理解するようになってきていました。そうであったからこそ、米国政府は、1937年からの「無条約時代」を迎えて、超厖大な軍拡計画の策定・実施に踏み切ることができたのであり、第2次大戦で枢軸陣営に圧勝しえたのです。
戦後の1980年代の米国でも、「反ケインズ主義者」であったはずのレーガン大統領が、ボルカー連銀議長(当時)に足をとられながらも、実際には、事実上のケインズ的大型積極財政の断行による軍事力の強化を大規模に推進し、軍備競争でソ連を圧倒して、冷戦の勝利を導いています。
このような戦前・戦後の歴史的事実にてらしてみましても、今日、中国の異常に急速・大規模な軍備拡張や北朝鮮の核武装化などに直面して、わが国の防衛力の整備・強化や国力の振興が喫緊の肝要事とされるにいたっているという情勢を想うとき、私(丹羽)は、わが経済政策当局が(したがって官庁エコノミストたちが)、近年のはなはだしい「反ケインズ主義」の知的混迷状態から、一刻も早く、覚醒することこそが、まさに救国のための必須の条件であると、強調せざるをえないしだいです。
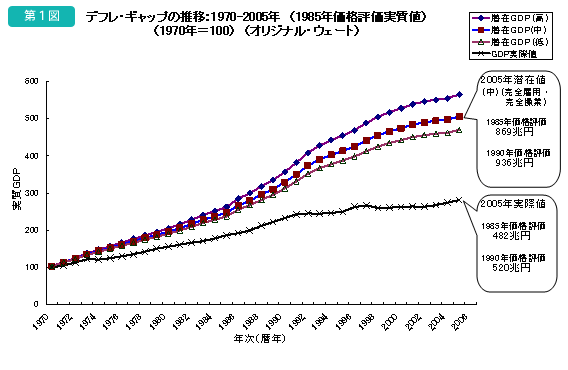
〔注〕 本図作成にあたってのデフレ・ギャップの推計・計測の方法、ならびに、典拠した資料等については、丹羽の著書『新正統派ケインズ政策論の基礎』 (学術出版会、平成18年刊)に詳述されている。なお、本図でのGDP概念は、わが国では2000年度まで公式に用いられていた< 68 SNA?> 算定方式の ものに、統一的に準拠している。
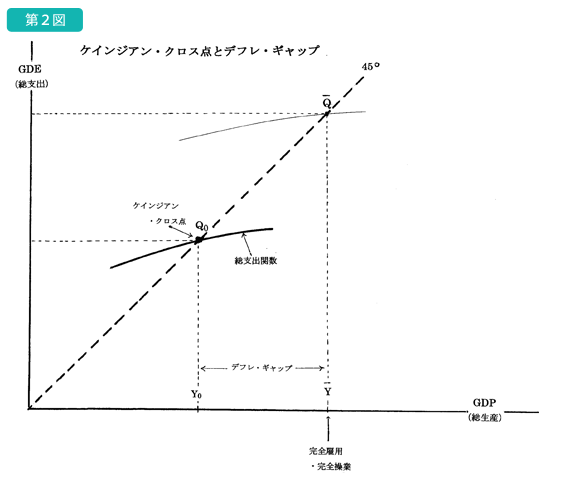
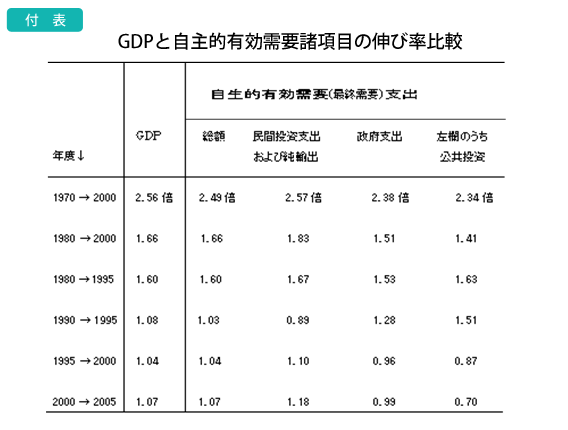
論 文
- 1.政策要求書 : 政策要求書本文、詳論および別表(平成10年9月)
- 2.建白書 : 小泉首相あて建白書「打ち出の小槌」を振る決断を!(平成14年1月)
- 3.建白書への補論 : 政府貨幣と日銀券の本質的な違い(平成14年1月)
- 4.日本経済政策学会 :日本経済政策学会共通論題セッション丹羽報告(平成10年5月)
- 5.Deflationary Gap:東アジア経済学会第6回世界大会丹羽報告(平成10年8月)
- 6.スティグリッツ提案弁護 : スティグリッツ氏の提案は間違ってはいない(平成15年7月)
- 7.日経モデルの問題点 : 日経モデルの問題点(平成15年6月)
- 8.特別論説: ルーカス型総供給方程式の一般化(詳論)(平成13年9月)(pdf:219KB)
- 9.Deflation Gap : -続-デフレ・ギャップ計測−続(平成14年 12月)
Abstract(要約)(pdf:22.2KB) 本文(pdf:585KB)
- 10.政策提言(平成18年秋 ):簡潔明瞭でインパクトのある政策案マニフェスト提案
- 11.危険! 19年度国家財政 :新年度のわが国家財政危うし(『月刊日本』19年2月号)
- 12.重要国策の遂行は絶望 :
マクロ経済学という科学を捨てては重要国策の遂行は不可能(『自由』19年6月号)
- 13.新古典派は市場原理否認:新古典派「反ケインズ主義」は市場原理を尊重していない(『自由』19年7月号)
- 14.「内閣府推計批判」:「内閣府の需給ギャップ推計値は誤りと欺瞞の極致だ!」(「月刊日本」平成19年9月号)
- 15.巨大地震活動期に備えるマクロ政策体系の構築 -「第3の財政財源」確立の方法論を中心に-
- 16.有効需要に生産は即応しうる― 周知の「過剰決定」問題解決として(詳論)
- 17.2013年ケインズ学会大会報告論文
Abstract(要約)(pdf:22.2KB) 本文(pdf:585KB)
